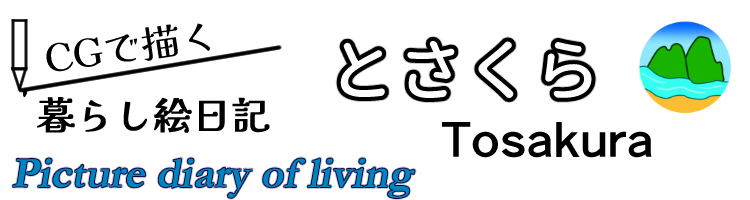四国の四県は、どんな形でどの位置にあるでしょうか?
学校で47都道府県を習った記憶があっても、正確な形や大きさまで覚えているでしょうか?
自分の住んでいる地域なら分かる、という言う人も多いかもしれません。
このサイトでは、四国四県について紹介していきます。
四国四県の形
全国47都道府県の名前と位置を覚えていても、全県の正確な形を認識している人はどれくらいいるでしょうか?
地図パズルゲームならできそうですが、各県の正確な形を書けと言われると・・・なかなか難しいかもしれません。
四国に住むことが決まったとき、えーっと・・四国地方・・と地図を思い出しました。
まず上側には香川県で面積は小さめ、右側に徳島県、左上に愛媛県、下に高知県・・・。
ここまでは浮かびましたが、各県の形が出てきませんでした。
地図を確認したら、四国の下半分のほとんどが高知県でした。高知県は東西に長い県なのです。
高知はほとんど山
四国四県の面積は広い順から高知県>愛媛県>徳島県>香川県です。
日本全国では、一番広い県は北海道、一番面積の小さい県は香川県。
が・・・可住地面積の順番は違います。
可住地面積というのは、総土地面積から林野面積と湖沼面積を除いたものです。
つまり人が住むことができる面積のことです。
調べてみたら、可住地面積率が一番低い県は高知県で約16.3%でした。
森林率(森林面積の割合)を見ると、高知県は80%を超えています。
つまり、高知県は、面積は広いけれどほとんどが山。
香川県は、面積は小さいけれど、高知県より平地の割合は高いのです。
年間降雨量も日照時間も、高知県は全国の中で一位争いをしています。
反対に香川県は降水量が少ない県で、香川県に行くとあちこちにため池があります。
そのため稲作より小麦の栽培が行われたと言われています。
その上、瀬戸内海でいりこが獲れ、塩と醤油が作られていて、美味しい讃岐うどんが誕生しました。
その他には和三盆や希少糖も有名です。
愛媛県は東予、中予、南予で雰囲気が違う気がします。特産は柑橘類、そして真鯛の養殖が有名です。道の駅で柑橘ジュースの飲み比べをしたことがありますが、どれも美味しい。愛媛の味付けは甘めです。
高知の人はうなぎを好んで食べますが、愛媛の人は穴子を食べます。
徳島県は、阿波踊りや鳴門の渦潮が有名ですが、農産物では、すだち、鳴門金時(さつまいも)やワカメが美味しいです。
おすすめは阿波尾鶏。徳島に行ったときにはぜひ食べることをおすすめします。鶏肉は鮮度落ちが激しいので現地で食べると味がひと味違います。本当に噛むほどにうまい阿波尾鶏。
え?高知県についてですか?
高知県については、これからゆっくり描いて行く予定です。